遠足

フィルメックス特別招待作品のラインナップ、ツァイ・ミンリャン!ホン・サンス!ジョニー・トー!ジャ・ジャンクー!フィルメックスらしい!とスクロールしていたら、最後にオリヴェイラ『繻子の靴』(410分/日本初上映)とあったので、え!って声が出た。
https://filmex.jp/2019/news/information/tokyofilmex2020_lineup_specialscreening
これまで観た長尺映画、
・クローズ・ランズマン『SHOAH』567分@イメージフォーラム
・フレデリック・ワイズマン『臨死』358分@ユーロスペース
の順だったけれど、『繻子の靴』は『SHOAH』の次の長さになる。『SHOAH』は4部に分けて上映され、1部ずつでも観られたけれど、こういうのって一気に観ないと一生観ないよね?と有給とって丸一日で全部観た。休憩は都度あるものの毎回退出→再入場を求められ外出可能な隙間はほぼないと事前情報を仕入れたので、朝イメフォ近所のおにぎり屋さんでおにぎり調達し(パリパリ音が鳴らないようラップで包んでもらう工夫)、珈琲、お茶、野菜ジュース、おやつも持参。出かける前にバッグに詰めてる時、完全に遠足に行く気分だった。
まだ『繻子の靴』のタイムスケジュールは発表されれおらず、しかし有楽町朝日ホール、アテネフランセ文化センターの二択を迫られ、どちらも長尺映画にまったく向かない座り心地の椅子なので、今から秋の遠足に向け体力を増強しておく所存です。
フィルメックス、さらに長い480分の映画もあって、ずいぶん迫力あるラインナップ。
<最近のこと>
今夜は『キングオブコント』決勝で、楽しみです。私の推しはニューヨーク!去年M-1にも出ていたけれど、コントの方が面白いと思う。
公式Youtubeに上がってる『ヤクザ』ってコントが一番好きだけれど、今夜はどのネタをやるのかな。『ヤクザ』、『アウトレイジ』好きな方も是非。Youtube、芸人さんのYoutubeで一番面白いと思ってて、毎日更新されるので毎日寝る前に観てます。
https://www.youtube.com/watch?v=UuRIcNfpFt8
瞬殺

下の日記でわくわくしていた『麒麟がくる』の、永禄の変(室町幕府13代将軍足利義輝が、三好義継・松永久通らの軍勢によって京都二条御所に襲撃され、殺害された事件)、冒頭から2分で終わってしまって唖然とした。
けれど番組終了後、記事を見つけて読んで納得。
https://news.mynavi.jp/article/20200920-kirin/
剣豪という描写もじゅうぶんではなかったし、あれほど人生の秋を匂わせていた人がいきなり派手な立ち回りを披露するのは唐突感があるというもの。刀一本だけ振り回して最期を迎えた義輝、向井理の殺陣は優美な舞のようでした。
畳に名刀突き刺す演出って、過去の映画であるのかな。あるなら観てみたい。

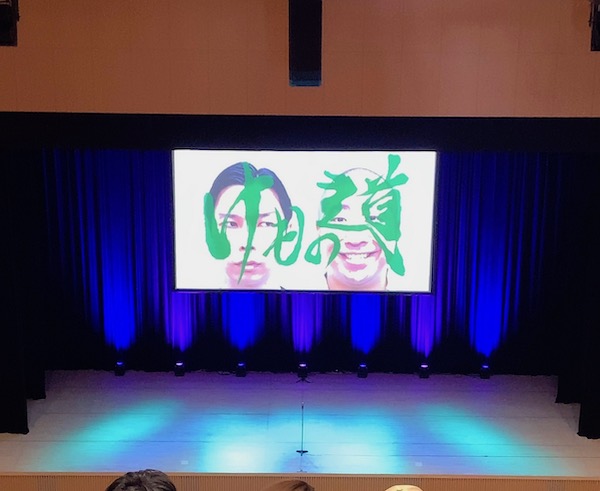
<最近のこと>
連休のお出かけ。ずいぶんぶりにホールという場所に行った。LINE CUBE SHIBUYAは旧・渋谷公会堂。ハライチのトークライブ「けもの道」に!
自由時間が週に1時間しかないなら何をする?って己の優先順位の確認に適した問いだと思うけれど、1時間なら映画やドラマではなく、『ハライチのターン!』(TBSラジオ/木曜深夜0時)をタイムフリーで聴きながら散歩したいです。ずっと聴いてる一番好きなラジオで、自粛期間中に映像も音楽も触れる元気がない…と言った人々に薦め、かなりの確率で沼に陥れました。ラジオいろいろ聴いてみたけれど、トークの内容はもちろん、自分好みの声のトーンか否かは聴き続けるための最も大事な要素だと思った。
ライブの詳細はこちら。後から発表されたゲストはオードリー!春日さんがピンクベストで胸を張ってゆっくり登場した時、会場にスタア登場!のざわめきが充満していた。
https://www.oricon.co.jp/news/2172607/
うまく聞きうまく話すことは技術が必要で、さらに自分だけの色を加え、さらに笑いを誘うことなんて努力しても達成の難しいことだけれど、「話芸」というものの最高峰・しかし肩の力は抜けている、を見せてもらって大満足。願わくば漫才をもう1本見たかったけれど。
記事を読んで知ったことに、ずいぶんなプラチナチケットをよく買えたなぁ!今年の運の大半を消費してしまっても後悔はない。
刀剣

エネルギーが回復したので、今年観た映画について徐々に記録していきたいと思ってます。時折、TVや配信で観たものについても。
これは6月の写真、自粛明けすぐに行ったのは東京国立博物館。埴輪もマスクをしておるよ。1月にメンバーパスを買ったけれど、1〜2度行ったのみで長い閉館に入った。再開後、閉館期間中のメンバーパス期限は延長してもらえました。事前予約して入館するシステムで、30分単位で入館人数上限が決まっているので、空いていて快適に観られる。
今年は大河ドラマ『麒麟がくる』を熱心に観ているので、刀剣や甲冑のエリアをじっくり観た。再開当初の目玉は平安時代の名刀『大包平』の展示。
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/201/297

空いている館内でこの前にだけ行列ができ、職員による誘導があった。刀剣ブーム(刀剣乱舞の影響?)によるものか。詳しくないけれど、実用の道具として作られたものだろうから、この刀も人をたくさん斬ったのだろうけれど、刃こぼれが一切なく作ったばかりのような美しさ。やわらかいものしか切っていないうちの包丁のほうがよほど傷んでいる…。これまであちこちで観た刀剣の中でも格別の妖気を放っていた。
『麒麟がくる』、将軍・足利義輝(向井理)の権力がいよいよ風前の灯火で、向井理の儚い表情を堪能する時間(向井理は死んだ魚の眼の時がもっとも美しいから、いつまでも死んだ魚の眼を堪能できる役柄を演じてほしい)なのだけれど、これまでほとんどその描写はないものの、足利義輝は剣豪で、畳に何本も突き刺した名刀を代わる代わる振り回して善戦したものの、しかし最期は畳を盾に串刺しされ亡くなった説がある人なので、今夜の『麒麟がくる』でその場面を観られるかしら、とドキドキしている。予告で障子に囲まれる向井理の姿までは確認しました。この時、畳に突き刺した名刀とは何か?も諸説あり、大包平もその名刀のひとつ、という説もあるらしい。こんな妖気漂う刀を振り回す義輝さまー!
現在、『大包平』の展示は終わり、『三日月宗近』の展示が始まったそうで、そちらも観てみたいです。
https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=6224
映画の秋

ご無沙汰しております。唐突ながら、最近食べたケーキです。立体的!

フォークでひと突き。ま、そうなるよね。食べるってそういうこと。この後さらにグロテスクな展開になったけれど自粛。以前食べたペンギンケーキは中がカシスのムースで、血の色に似ていたけれど、あれに比べるとこちらは穏やかな色調。

池袋、メトロポリタンホテルはペンギン好きの聖地であった。
ここ半年ほど、身体が先に新しい世界に強制的に足を踏み入れ、気持ちが追いついていない状態だったけれど(そういう時に文章を書くのはなかなかしんどく、日記が疎かになっていた)、8月後半にバラバラになった感覚が統合する瞬間が不意にあり、待ち望んだエネルギーが回復してきた感がある。
過去に自分が経験した中では中国に行った時、身体はすでに移動していて、感覚のうちいくつかは準備はできているけれど(特に言語感覚のうち、読み書き聴くはある程度整っていた)、話すハードルが高く、徐々に微細な発音の難しさが原因だと思い当たり、マンツーマンで発音だけ矯正してくれる先生を探し交渉して毎週通い、1ヶ月ほど過ぎた後に突然バチっと感覚が統合する瞬間が訪れ、以降すらすら話し通じるようになった時と似ていた。あんな興味深い瞬間は二度と人生には訪れないだろうと思っていたけれど、予期せぬ疫病によって再度もたらされた。
自粛中にどう過ごした何を観た、という話は何人ともしたけれど、こういう身体感覚の話を誰かとしてみたいな。
エネルギーが回復した途端、急に忙しくなったので、何年かぶりに手帳を買い、公開される映画の情報も調べて書きこんでみたけれど、東京国際映画祭もフィルメックスも無事開催されるのですね。
東京国際映画祭は 10/31(土)〜11/9(金)。今年は部門を減らして統合したり、フィルメックスとの連携があったりするようです。ラインナップ発表は9/29(火)。
東京フィルメックスは10/30(金)〜11/5(木)。例年より早い時期の開催で、東京国際映画祭と時期が重なるので要注意。
https://filmex.jp/2019/news/information/filmex2020
週末にしか行けないかもしれないけれど、こんな年にも東京に映画の秋がやって来ることが嬉しいです。
厄難祓除

ご無沙汰しております。感染者数が鰻登りで、いよいよ魔都という言葉が似合ってしまう様相の東京ですが、私は(今のところ)元気です。
緊急事態宣言解除以降、しかしワクチンも特効薬もない中で楽観的になる理由もないな、と行動の何をどこまで解除して良いものか判断がつかず、出社は電車が空いてる時間を選んで週2回、近所で外食数回、時間指定で予約して歩いて行ける博物館に2回、国立映画アーカイブで古い映画1本、新作映画を観るタイミングを伺っているうちに感染者数が増えてきたので映画館行き自粛解除は当面保留、という感じの生活です。
映画や動画を観ることについては、
・配信系はNetflixとamazon primeに登録。今のところは必要十分。
・映画館の割引特典を使うために日本映画テレビ技術協会の個人会員を数年間更新していたけれど、しばらく映画館通いが難しい状況は続くだろうと3月末で退会。
・通勤時間の音楽用だったSpotifyを通勤が減ったので解約し、Youtube Premiumに登録。広告を飛ばせるのは大変便利なもので、Youtubeを観る時間がぐんと増える。
などウィルス感染拡大がもたらした変化とはいえ、私の行動レベルにおいてもこれが時代の変わり目か…という気分。

<写真上>
根津神社、夏越しの大祓は中止。茅の輪は設置しておくから「各自自由にくぐってください」とお知らせがあって、「各自自由にくぐってください」って表現が面白いな、と思いながら自由にくぐったけれど、自由くぐりは今年だけで終わるといいなぁ。
<写真下>
不要不急の外出自粛の連休のお供。リアルな粽は作り手の引退により粽の絵の御札で代用されることになったそう。神社に行っても開運!などゆるふわではなく、自分と周囲が健康でいられますように、どうか!と祈るばかり。神頼みってこんな逼迫した時に生まれる感情なのか。ぐぬぬ…もう大仏建立するしかない!って昔の人が決めてあんな巨大なものを一生懸命作るに至った混沌を少し理解した。ペンギンラベルのボトルは引越し祝いにいただいた日本酒です。
TOHOシネマズでジブリ旧作がかかっていて贅沢でいいなぁ!と眺めながらも、行くのは難しい…でもあまり観ていないジブリを観る機会は欲しい…と区の図書館で調べて、DVDを借りることに。まず借りられた『耳をすませば』を連休中に観る予定。私が利用する館は(今のところ)無事だけれど、区内の別の図書館の職員の方が陽性確認されたそうで、そちらは休館になった。これが都民の日常にじわじわ迫りくる恐怖というものか。
大河

外出のひとつひとつに言い訳めいた説明を求められる感があるけれど、必要な外出と自分で認定し、根津神社に月はじめに行き月次花御札を授かる、は継続している。
例年であれば露店が出て、千駄木や根津の駅から人の波ができる恒例のつつじまつりは、今年は中止になった。つつじ苑への立ち入りも禁止。しかし季節どおりにつつじは咲いており、空いた時間を狙って境内から遠巻きに眺めることはできる。

ソーシャル・ディスタンシング・参拝

5月の御札は菖蒲。右の薬玉は、夏の邪気を祓うため5月端午の節句から、9月重陽の節句まで飾るもの。
中華圏のニュースを現地のメディアから摂取して1月下旬から自主的に自粛生活に入ったので、最後に映画館に行ったのは1月。Netflixもamazon primeも、それらをミニシアターサイズの画面で観られる装置も部屋にあるけれど、気分の問題で映画ぶんの長さの集中力を作るのが難しく、時間ができたら観ようと積んでいたあれこれは、時間ができたからといって観られるものでもないんだな、を実感中。
目下の最大の楽しみは、大河ドラマ『麒麟がくる』です。観たい意欲はあるけれど歴史に明るいわけではない自分は、武将の名前、血縁・主従関係を把握しきれず混乱して脱落しそうだな、と思ったので、近所の書店の前を通りかかった時、公式ガイドブックが売られているのを見かけて初めて買ってみた。これがなかなかの良策で、放送開始前にその日のあらすじを軽く読み、見慣れない名前があったら相関図を確認、それでも不明点があったらwikiなどで調べる、を繰り返し(試験勉強みたい…)、今のところ脱落していないどころか、最高に面白い!
斎藤道三(本木雅弘)と高政(伊藤英明)の父子関係は、高政のカイロ・レンばりの拗らせ感が『スター・ウォーズ』的で、道三が土岐頼芸(尾美としのり)の鷹を皆殺しするくだりは『ゴッドファーザー』のベッドに馬の首事件のようだった。光秀は今のところフラストレーションを溜め込む中間管理職的人物として描かれ、信長&帰蝶夫婦は無邪気で可愛らしく、底知れぬ不敵さ。史実をベースに創作がふんだんに盛り込まれているのだろうけれど、歴史、なんとドラマティック…(興奮)!!
明日の放送は斎藤道三ってどういう人生だったっけ…とググった時から楽しみにしていた長良川の戦い!予告を何度も観て気持ちを高めているところ。脚本、キャスト、歴史そのものの魅力に加え、大河ドラマってCMなし45分の短さがちょうど良い。映画のための2時間の集中力は難しくとも、45分なら大丈夫という現在、そのうち世界が落ち着き、自分も回復するとまた映画にどっぷり没入できる日も来るのだろう。
麒麟がくる
https://www.nhk.or.jp/kirin/
読み込んでいる公式ガイドはこちら。実用の書。
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069233832020.html
4月の現状

ご無沙汰しております。お元気ですか。
外に一歩足を踏み出せば、たちまち人と触れ合ってしまう都心暮らしですが、私は元気です。家族、同僚、近くの友人も遠くの友人も、知る限り陽性者も疑いの人もおらず、このまま誰も煩わうことなく、この特殊な日々を乗り切れたらいいな、と願っています。これを読んでくださっているどこかの街のあなたも、あなたの身近な人々も、ご無事でありますように。
全国のミニシアターを救うべく立ち上がったクラウドファウンディング、
https://motion-gallery.net/projects/minitheateraid
会見はDOMMUNEで聴いていたけれど、どのコースにするかちゃんと読んで検討しよう、と思ってる間に4月が終わるので、連休中に決めて支払いたいと思っています。
コースによってはリターンに含まれる「ミニシアター・エイド基金」特別ストリーミング配信サイト「サンクス・シアター」の作品群が魅力的で、気になりながらも見逃していたものが多い。濱口ファンとしては『何食わぬ顔(long version)』『親密さ』が含まれていることに!!!の気分。『親密さ』なんて4時間超えの映画だから、家に篭って何もやることがなーい期にぴったりすぎる。
という感じで日記もそろそろ復活していきますので、また遊びにきてください。素敵な連休になりますように。
<photo>東大本郷キャンパスの桜。開門時間であれば入り放題なので近隣住民の憩いの場だけれど、緊急事態宣言以降、出入り禁止になった。
【about】
Mariko
Owner of Cinema Studio 28 Tokyo
・old blog
・memorandom
【search】
【archives】
【recent 28 posts】
- 1900s (2)
- 1910s (5)
- 1920s (8)
- 1930s (25)
- 1940s (18)
- 1950s (23)
- 1960s (58)
- 1970s (13)
- 1980s (40)
- 1990s (45)
- 2000s (34)
- 2010s (237)
- 2020s (21)
- Art (27)
- Beijing (6)
- Best Movies (5)
- Book (47)
- Cinema (2)
- Cinema award (15)
- Cinema book (58)
- Cinema event (95)
- Cinema goods (14)
- Cinema history (2)
- Cinema memo (123)
- Cinema Radio 28 (8)
- Cinema Studio 28 Tokyo (88)
- Cinema tote (1)
- Cinema Tote Project (1)
- Cinema trip (43)
- cinemaortokjyo (2)
- cinemaortokyo (73)
- Drama (3)
- Fashion (39)
- Food (61)
- France (15)
- Golden Penguiin Award (9)
- Hakodate (6)
- Hokkaido (3)
- HongKong (3)
- iPhone diary (1)
- journa (1)
- Journal (242)
- Kamakura (1)
- Kobe (1)
- Kyoto (18)
- Macau (1)
- memorandom (4)
- Movie theater (202)
- Music (41)
- Nara (15)
- Netflix (3)
- Osaka (2)
- Paris (13)
- Penguin (15)
- Sapporo (3)
- Taiwan (44)
- TIFF (24)
- Tokyo (340)
- Tokyo Filmex (14)
- Weekly28 (10)
- Yakushima (3)
- Yamagata (11)
- YIDFF (6)
- Yokohama (3)
- Youtube (1)
